
マインドフルネスの効果は絶大です!
・集中力のアップ
・心が穏やかになる
・幸福度が上がる
・ストレスの減少など様々あります。
しかし、いざやってみると
「マインドフルネスがなかなかできない」
「マインドフルネスって瞑想すること?」
「マインドフルネスのコツってあるの」
などマインドフルネスはなかなかつかみどころがなく、どういったものであるのかわかりづらいと思います。
ストレスを減らすつもりが、なかなかできなくてイライラしてきてかえってストレスになるくらいです・・・
そこで今回、そんな「マインドフルネスができない」という悩みにお答えします。
なぜ、マインドフルネスができないと感じてしまうのか
マインドフルネスな状態はどのような感じか
マインドフルネスの実践方法など
具体的に解説していきます。
この記事を読み終わった頃には
「マインドフルネスをこんなふうにやればいいんだ」ということがわかります。
そして、マインドフルな心の状態を味わい、集中力も高まるでしょう。
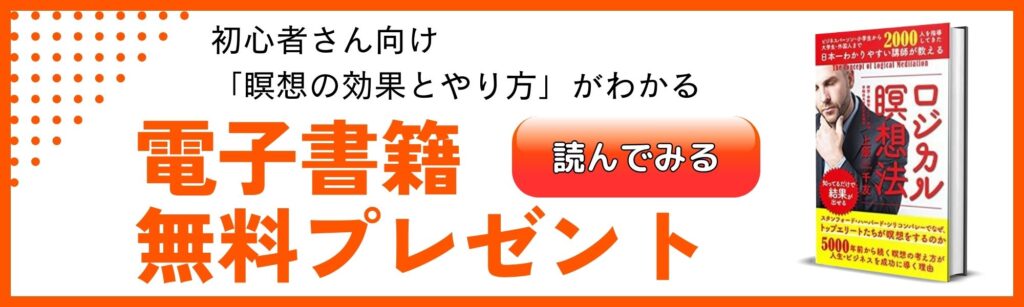
もくじ
マインドフルネスができている?できていない?
ではまず、マインドフルネスとは何かということを明確にしましょう。
カリフォルニア大学のバークレー校の論文によるとマインドフルネスとは
自分の思考、感情、身体感覚、周囲の環境を瞬間ごとに意識し続けることを意味します。
さらに
自分の考えや感情を判断することなく、たとえば、特定の瞬間における考え方や感じ方に「正しい」または「間違った」方法があると信じずに、それらに注意を払うことを意味します。ともあります。
これが「今、ここを感じること=マインドフルネス」なわけです。

これが定義としてはそういうことなのですが、実際「これだ!」と感じることが難しいですね。
そこで、マインドフルネスではない状態、これをマインドレスネスというのですがこの状態を理解するとマインドフルネスを理解しやすくなります。
なぜなら、私たちはよくその体験しているからです。
例えば、マインドフルネスが「今の自分の思考、感覚などに瞬間ごとに意識し続けること」であるなら、その反対は「今の自分の思考、感覚などを意識せず、他のことを考えることです」
それは、今、仕事でパソコンを打ちながら
「ああ、これ終わったらあれやらなくちゃ」
とか
「今晩何を食べようかな」
とか
「あんなこと言わなければよかった」
など様々な今目の前の仕事ではないことを考えてしまうのが、マインドフルネスとは逆の状態です。
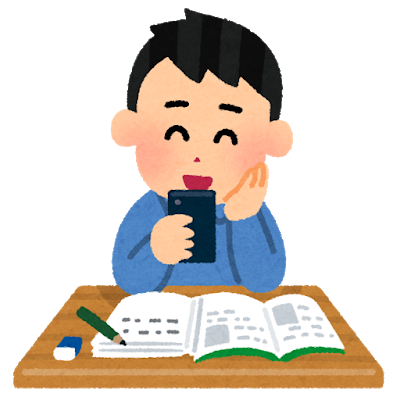
これは私も、誰でも経験したことがあると思います。
この今ここだけに意識が向けられないのは、ごくごく普通に起こる現象です。
しかし、このマインドフルネスとは逆の状態は実は
・脳に負担をかける
・結局、労働効率が落ちる
・ミスも多くなる
・脳も心も疲れる
という状態であるのです。
ですから、なるべくマインドフルネス=今ここに意識を向けられるようになりたいものです。
そうすると
・脳に負担をかける → 脳が最適な状態
・結局、労働効率が落ちる → 労働効率アップ
・ミスも多くなる → ミスが少なく
・脳も心も疲れる → 脳も心も疲れにくい
そして
・幸福感が下がる → 幸福感が上がる
となるはずです。
以上、マインドフルネスの反対の状態からマインドフルネスをご理解できましたでしょうか。
マインドフルネスができない理由
では、なぜマインドフルネスができなくなってしまうのかその理由を考えてみましょう。
マインドフルネスができない主な4つの原因
1 内部と外部の環境の影響によるもの
単純に自分の内部や外部の環境に気になること、刺激が周りにある場合、集中力が散漫になりマインドフルネスでなくなることがあります。
それは、例えば
内部環境:お腹が痛い、頭が痛い、胃腸が調子が悪いなどの体調不良の場合、あるいは座っていて足が疲れてきたなど
外部環境:周りの音がうるさい、気になる匂いがある、室温が暑い、寒いなど

これらの場合には、マインドフルネスどころではないのでどうしても意識が気になるところに向かってしまいます。
ですから、対処法としては物理的に静かで刺激がない場所で行う。一人になれる場所や時間を見つけましょう。
あるいはあまりにも体調不良の場合にはやらない、ということです。
2 マインドフルネスの誤解や誤ったイメージによるもの
マインドフルネスには、いくつかの誤解や誤ったイメージが存在します。
×「無になる」
×「空っぽになる」 などです。
まず、マインドフルネスが「ただ座って何も考えないこと」と捉えられることがありますが、実際には意識的な観察や注意の集中をしています。
また
×「リラックスしたい」
×「ストレスを解消したい」 などの誤解もあります。
マインドフルネスは「リラックスやストレス解消のための手段」と誤解されることもありますが、その本質は「現在の状況や感情に対してそれを受け入れること」です。
そして、自己の意識を深めることにあります。
ですから、ある意味リラックス状態とは反する意識が鋭い状態とも言えます。
そもそもこのような誤解があると「なんだか違う」「できない」と感じてしまうのは自然であると思います。
いかがでしょうか、誤解はなかったでしょうか。
誤解していた場合には、まずはマインドフルネス=無の状態ではない、と考えましょう。
それだけで「マインドフルネスができなかった」という否定的な気持ちは無くなると思います。
3 忙しさやストレスによる注意散漫な状態によるもの
「心ここに在らず」という忙しさやストレスの多い状況では、私たちの注意力が散漫になりがちです。
当然マインドフルネスな状態にはなりずらいでしょう。
多くのやるべきタスクや責任に追われる中では
・思考が過去の出来事や未来の予測に囚われたり
・心が不安や不満に取り憑かれたりします。

先の例でいうと、まさに
今、仕事でパソコンを打ちながら
「ああ、これ終わったらあれやらなくちゃ」
とか
「今晩何を食べようかな」
とか
「あんなこと言わなければよかった」
と考えている状態です。
これによって、現在の瞬間に意識を向けること、つまりマインドフルネスが難しくなります。
ですから、この対処法としては、まず自分の気持ちや感情に気づくことが重要です。
例えば
「ああ、私は今焦っているな」
とか
「昨日のことが気になっているから、また思い出しているのだな」
とか気づくことです。
そのような自己観察を通じて、忙しさやストレスによって心が乱れていることに気づくことができます。
この「今の心の状態への気づき」こそがマインドフルネスです。
自分の心の様子を客観的に、ちょっと離れたところから見てみる。
実はこれだけで忙しさへの嫌な感情やストレスを軽減できるのです。
そして、忙しいという事実に対してそれまでとは違って落ち着いた気持ちで向き合うことができるようになります。
↓ 平常心を保つ方法を知るなら・・・ブログ記事
4 過去や未来への執着によるもの
過去や未来への執着は、マインドフルネスの実践を妨げる要因の一つです。
過去の出来事「ああすれば良かった」「あんなこと言わなければ良かった」
未来の不確かなこと「心配だな」「これから先不安だな」などに執着しすぎると、現在の瞬間を見落としてしまいがちです。
マインドフルネスでは、過去や未来にとらわれずに、現在の状況に意識を向けることが重要です。
過去の後悔や未来の心配に囚われることで、ストレスや不安を引き起こし、集中力を奪ってしまいます。
繰り返しになりますが過去や未来への執着から解放されるためには、まずは自己の観察が必要です。
それは自分が過去や未来に囚われていることに気づき、それを受け入れることです。

こうすることで前述の「忙しさ」の例と同様に過去や未来に囚われていることから離れることができるのです。
マインドフルネスをスムーズに行う4つの方法
では、ここからマインドフルネスの基本的な実践方法の紹介を行います。
それらは以下の通りです。
1 呼吸にフォーカスすることでの集中力向上
2 五感を意識する
3 身体に意識を向ける
4 マインドフルネスの瞑想
どの実践方法にしてもマインドフルネス「今ここに意識を向ける」ことには変わりません。
では1つずつ紹介していきます。
1 呼吸にフォーカスすることでの集中力向上

やり方:
ステップ1 快適な姿勢で座り、目を閉じます
ステップ2 深呼吸をするために、ゆっくりと鼻から息を吸います
ステップ3 吐く息も同様にゆっくりと行います。
ステップ4 吸う息と吐く息に意識を集中し、息の出入りや呼吸の感覚を感じることに注意を払います。
ステップ5 心や体が落ち着いてくるまで、呼吸に集中し続けます。
ステップ6 思考が浮かんでも、ただ観察するだけで反応せず、呼吸に戻します。
ステップ7 呼吸の感覚に徐々に深く入り込んでいき、呼吸自体に溶け込むようにします。
感覚としては「吸ってるな」とか「吐いているな」とか、鼻の奥の方で空気が通る冷たさを感じるなどです。
注意点:
呼吸に集中する際に、無理な力を入れずに自然な流れに身を任せることが重要です。
初めは数分から始め、徐々に時間を増やしていくことをオススメします。
思考が逸れたり、落ち着かない場合でも、自己批判せずにただ観察し、呼吸に戻すことを心がけましょう。
呼吸にフォーカスするだけでなく、身体や感覚にも注意を払いながら実践することで、より深いマインドフルネスの状態に入ることができます。
↓ リラックスできる呼吸法について詳しくはこちらのブログ記事をご覧ください
2 五感を意識する
現在の瞬間に意識を集中させるために、五感を使って感じることにフォーカスします。
例えば、周囲の音、触れるもの、見えるもの、匂いや味など、感覚を通じて現在の状況を感じ取ります。
では、その中でも「食べるマインドフルネス」についてやり方を紹介します。

(静かな場所で食事をすることが理想的です。)
ステップ1 食べる前に深呼吸をして、心と体を落ち着かせます。
ステップ2 食べ物を選ぶ際、見た目や色、香りに注意を払いながら選びます。(なんでも良いですが、ドライフルーツなどがよく使われます)
ステップ3 食べ物を手に取ったり、口に運ぶ前に触覚を意識します。食べ物の質感や温度を感じます。
ステップ4 口に入れた瞬間、食材の味や舌の触感、口の中に広がる風味を感じるようにします。
ステップ5 噛む動作や咀嚼の感覚に集中し、食べ物をじっくり味わいます。
*飲み物を飲む場合も、温かさや冷たさ、口内での感触や味わいを感じながら飲みます。
注意点:
食べるマインドフルネスは、食事をゆっくりと味わい、感謝の気持ちを持って行うことが大切です。
食べ物に集中することで他のことに意識が逸れないように注意しましょう。(静かで気が散らない場所で行う)
食事を急いだり、自動的に進めたりすることを避け、食べるマインドフルネスの時間を確保します。
食事中の無駄話や他の刺激を避けるようにし、集中力を高めます。
3 身体の感覚に注意を向ける
身体の感覚を意識することで、現在の状態に集中します。
座ったり歩いたりする際の身体の感触や動き、筋肉の緊張やリラックスなど、身体の状態を観察します。

では、このマインドフルネスの実践例「歩くマインドフルネス」のやり方を紹介します。
(静かで安全な場所を選びます。公園や自然の中がおすすめです。)
ステップ1 背筋を伸ばし、自然な姿勢で立ちます。
ステップ2 深呼吸をして、心と体を落ち着かせます。
ステップ3 ゆっくりとしたペースで歩きます。一定のリズムを保つようにします。
ステップ4 足の着地や歩幅に注意を払いながら、自然な歩行を心がけます。
ステップ5 足の裏の感触や足首、ふくらはぎ、太ももなどの筋肉の動きを意識します。「足の裏の先が地面についている」「足が地面を離れる」などといった感じがします
ステップ6 姿勢や体重移動、腕の振りなど、全身の感覚を観察します。「ああ、ちょっと足疲れたな」「腕をあまり振っていないなぁ」などといった感じがします。
4 マインドフルネス瞑想
マインドフルネス=マインドフルネス瞑想と思っている方も多いかと思います。
ここでは、マインドフルネスの一種である瞑想として紹介します。

静かな場所を見つける: 騒音や他の刺激の少ない場所を選びます。
ステップ1 心地よい姿勢で座る:
座りやすい椅子や床に座ります。
背筋を伸ばし、リラックスした姿勢を保ちます。
ステップ2 目を閉じて呼吸に集中する
目を閉じて、自然な呼吸に注意を向けます。
吸う息と吐く息の感覚に集中し、呼吸を深く感じるようにします。
ステップ3 思考の観察
思考が浮かんできても、ただ観察するだけで反応せずに受け入れます。
感情が浮かんできても、ただ観察して、反応せず受け入れます。
つまり、呼吸、思考、感情を観察し続けるというのがマインドフルネス瞑想です。
注意点:
- 完璧さを求めずに受け入れることが大切です。マインドフルネス瞑想は習慣と継続によって深まっていきます。
- 初めは数分から始め、徐々に時間を増やすことが効果的です。
- 環境や体調に合わせて自分自身のペースで実践しましょう。
- 瞑想中に眠気がやってきた場合は、目を開けたり、体を動かしたりすることで気持ちを引き締めます。
マインドフルネス瞑想ができた時の感覚を解説しているブログ記事
瞑想を深めると、どんな感覚が起こるのか、まとめてみた
マインドフルネスができない理由とその解決方法をわかりやすく解説まとめ
・マインドフルネスとは「自分の思考、感情、身体感覚、周囲の環境を瞬間ごとに意識し続けること」
・マインドフルネスができない理由
1内部・外部環境によるもの
2マインドフルネスの誤解や誤ったイメージによるもの
3忙しさやストレスによる注意散漫な状態によるもの
4過去や未来への執着によるもの
・マインドフルネスの実践方法と注意点の紹介
1 呼吸にフォーカスすることでの集中力向上
2 五感を意識する
3 身体に意識を向ける
4 マインドフルネスの瞑想
・マインドフルネスのハードルと対処方法
心の乱れやストレスによるもの
無意識な習慣によるもの
環境の影響によるもの
妄想や過去・未来への執着によるもの
最後に、マインドフルネスをできるために大事なことは「マイペース」です。
マインドフルネスの習慣化には一定の時間がかかるため、自分のペースで取り組むことが重要です。
短い時間から始めて徐々に延長し、無理なく継続することがポイントです。
マインドフルネスの実践中に別の思考が浮かんでも、「集中してなくてダメだ」などと自己批判せずに受け入れる姿勢を持ちましょう。
自己観察を通じて気づき、自分自身への優しさを忘れずに続けることがポイントです
そして、マインドフルネスができるようになるために、さまざまな方法で一番やりやすいものを選んで、トライしてみてください。
また、飽きないように色々なマインドフルネスをその日によって変えてみるのもいいと思います。
この記事をご参考にぜひ、「今ここに意識を向ける」感覚を味わってみてください。
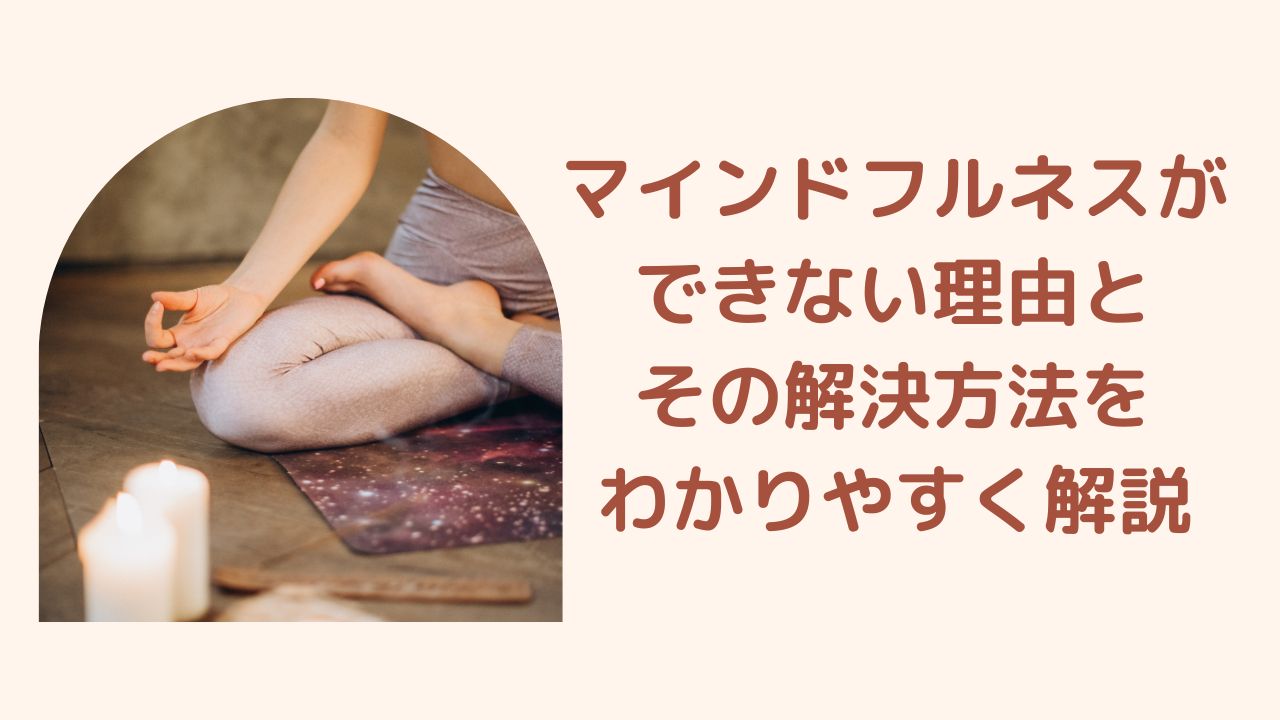
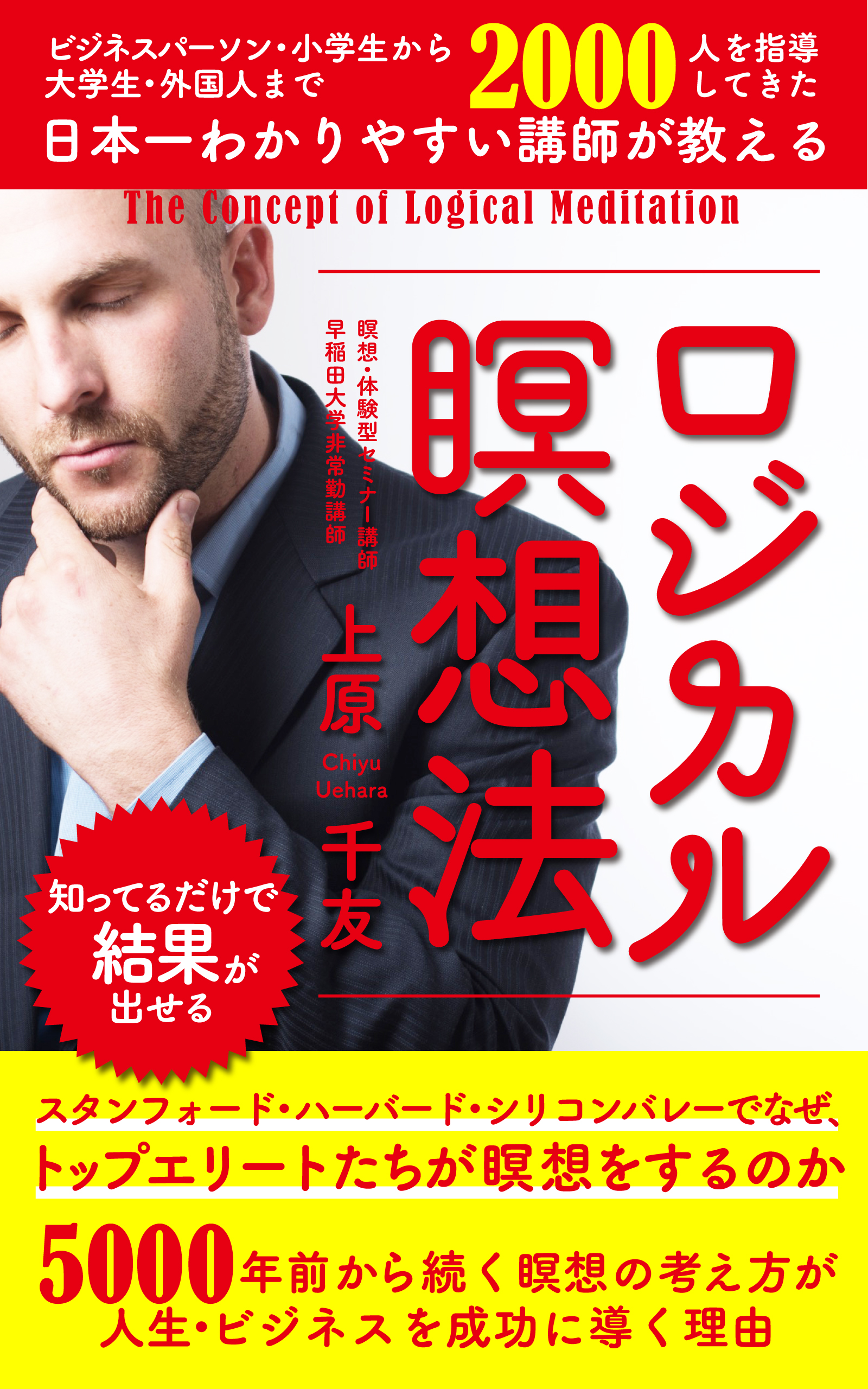


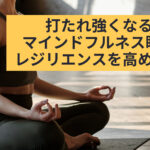

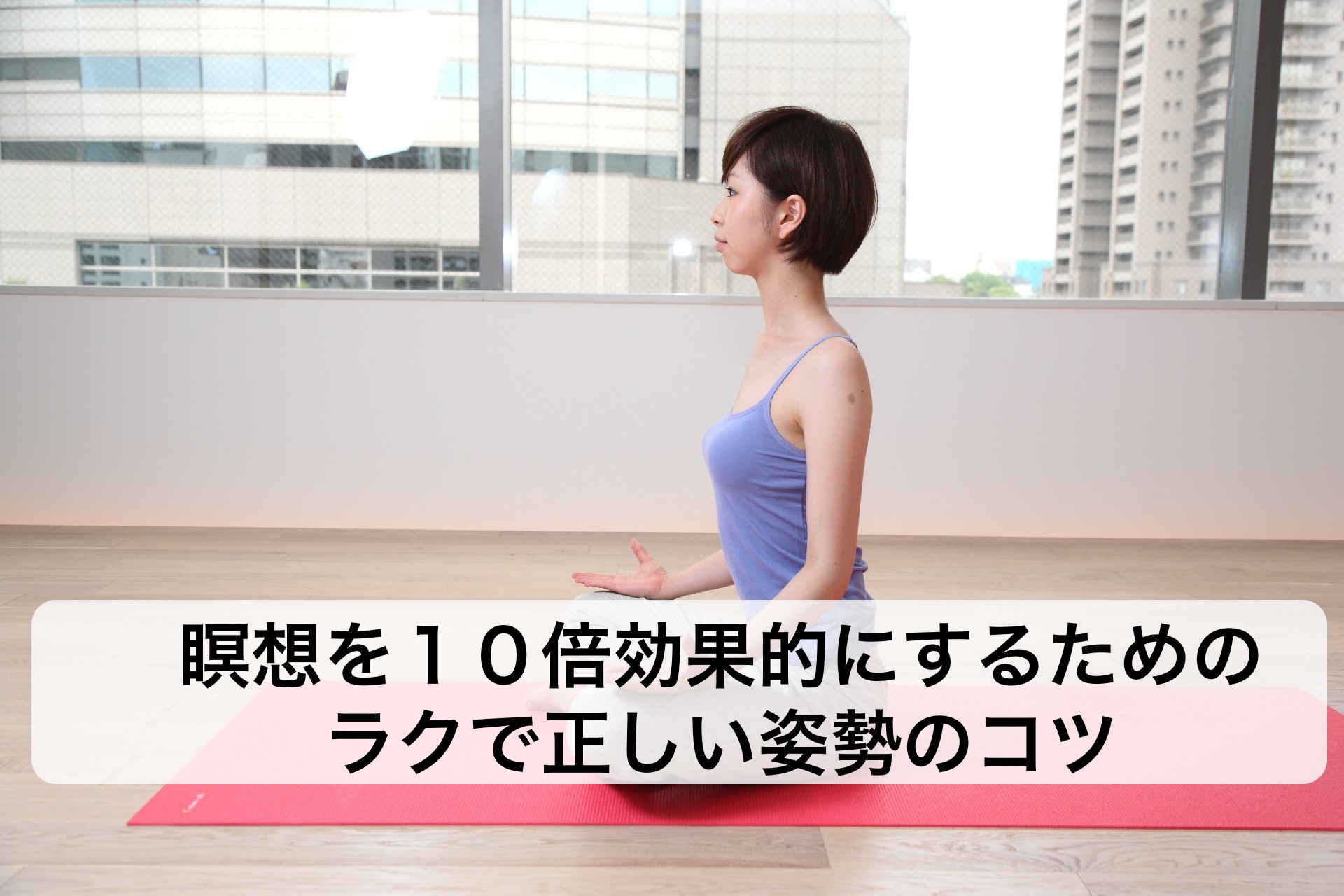

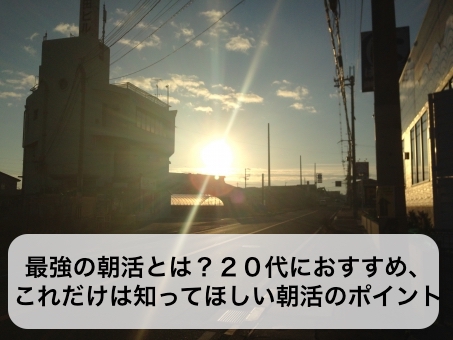
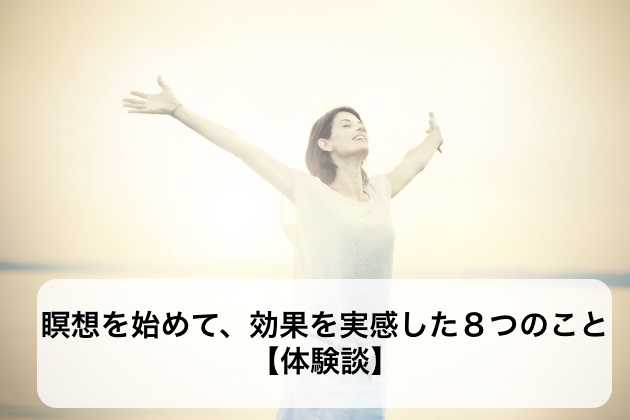
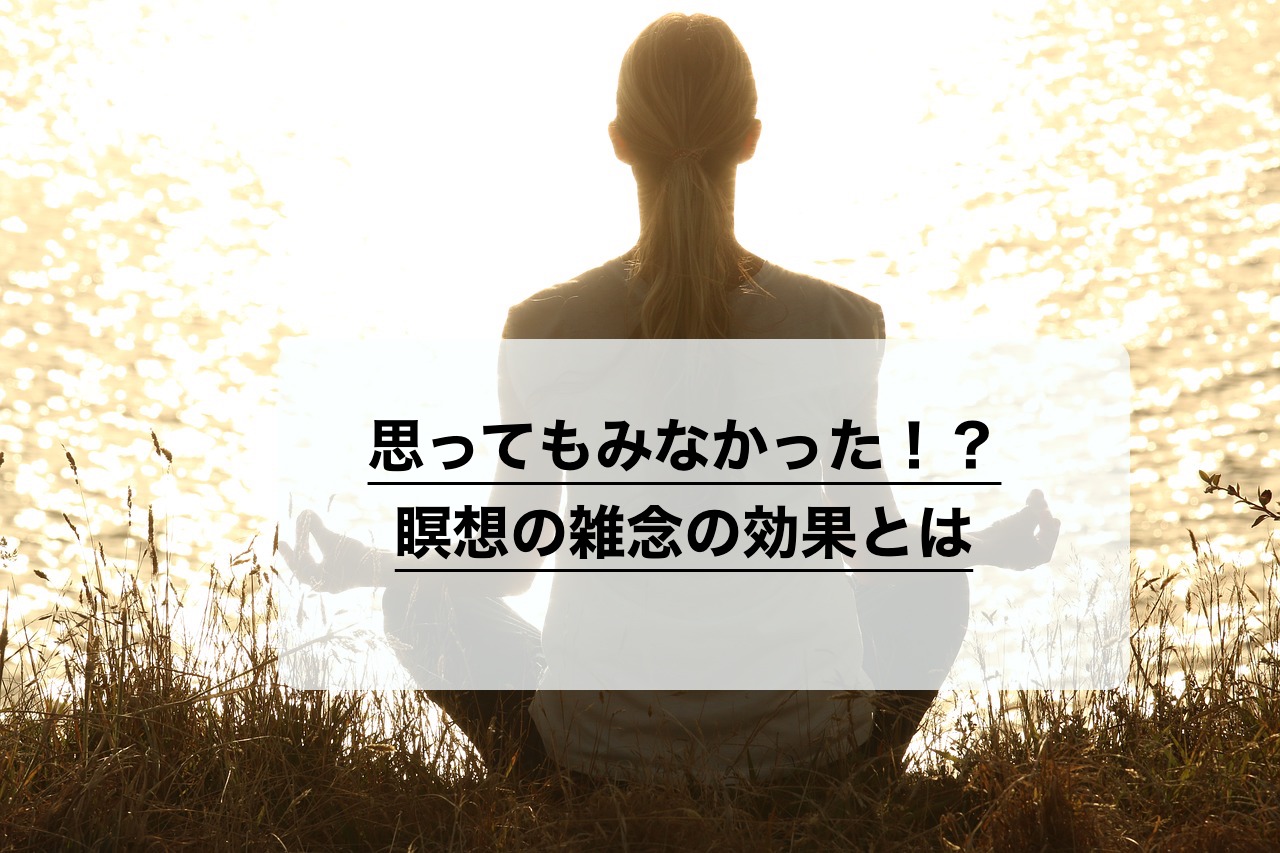

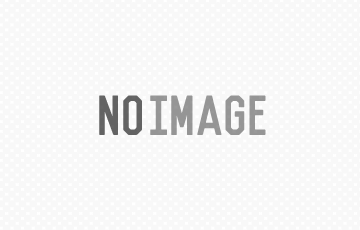
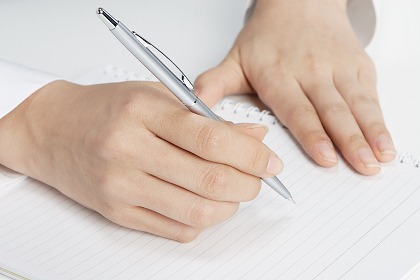




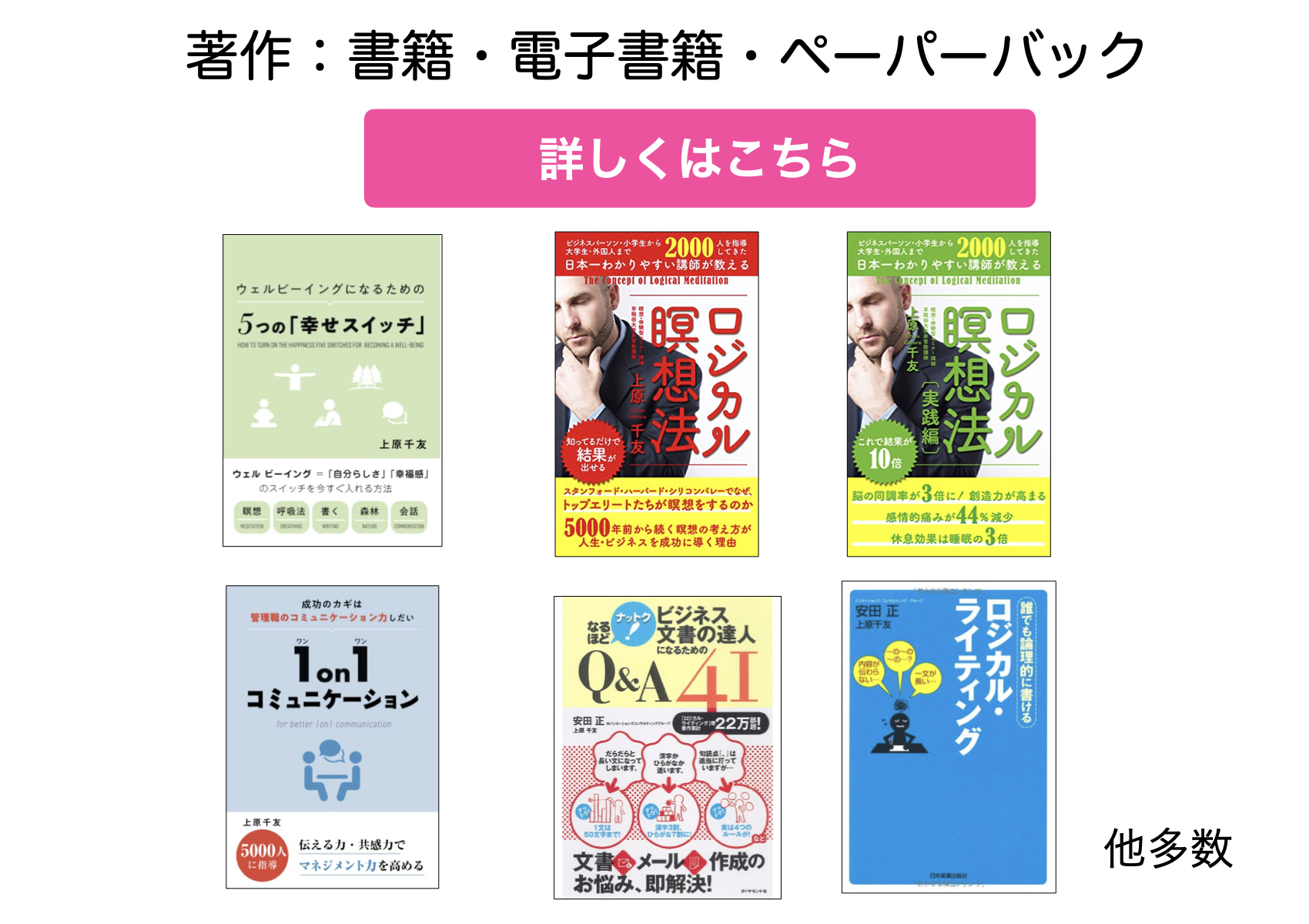
コメントを残す